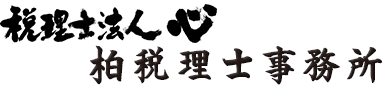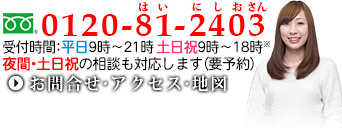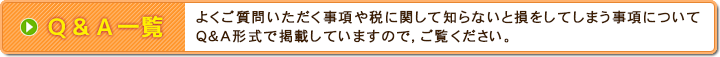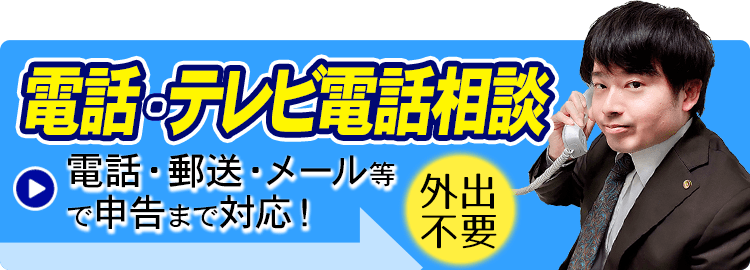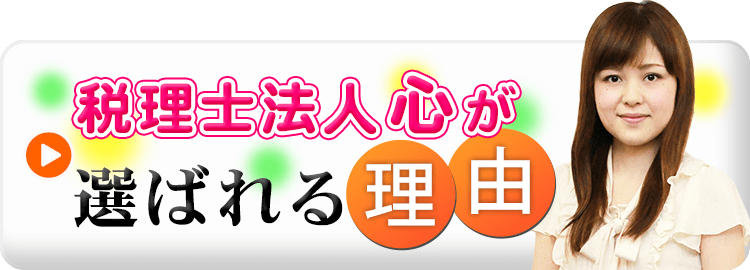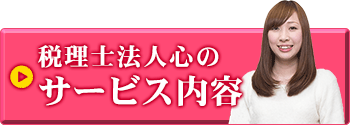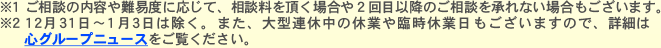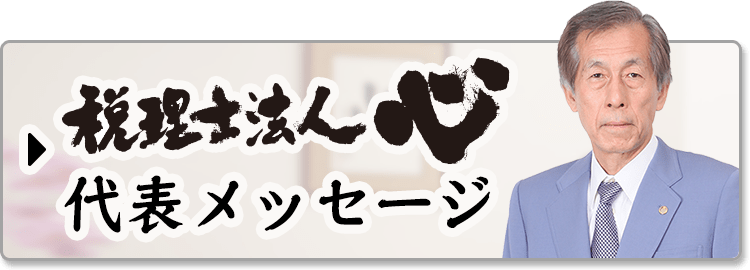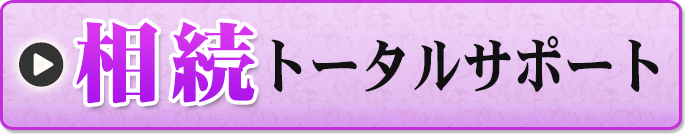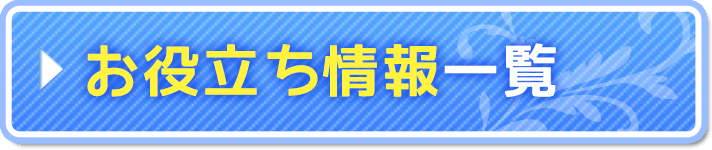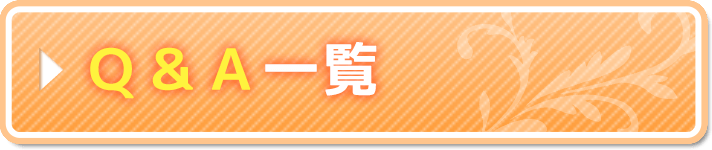消費税の免税事業者とは
1 消費税の免税事業者とは
消費税の免税事業者とは、一定の条件を満たした事業者に対して、消費税の納税義務が免除される制度の対象となる事業者を指します。
免税事業者は、消費税の申告や納付を行う必要がありません。
そもそも、消費税は、日本国内で商品やサービスの取引が行われた際に課される間接税で、最終的には消費者が負担します。
課税事業者は課税売上に基づいて消費税を徴収し、仕入時に支払った消費税を控除して差額を国に納付します。
ただし、免税事業者であることが、必ずしも取引先との関係で良いことばかりとは言えないため、免税事業者及び消費税の仕組みを正しく理解する必要があります。
2 免税事業者の要件
免税事業者として認められるには、以下の条件を満たしている必要があります。
① 基準期間の課税売上高が1,000万円以下
基準期間とは、原則として前々事業年度(2期前)の1年間を指します。
前々事業年度の課税売上高(消費税が課される売上高)が1,000万円以下であれば、免税事業者となる資格があります。
② 特定期間の課税売上高や給与支払額が1,000万円以下
特定期間(前年の1月1日から6月30日まで)の課税売上高または給与支払額が1,000万円を超える場合は免税事業者から外れます。
つまり、法人成りも含む、新規の事業者は、設立1期目や2期目については、基本的に、基準期間がないため自動的に免税事業者となります。
ただし、特定期間の条件があるため、課税売上高や給与支払額に注意をする必要があります。
3 免税事業者のメリットとデメリット
メリットは、消費税の納付義務がないため、納税負担が軽減され資金繰りが楽になることです。
また、消費税の申告書を提出する必要がないため、税務申告や会計処理が簡略化されるというメリットもあります。
デメリットは、仕入税額控除を受けられない、つまり、消費税を納付しないため、仕入時に支払った消費税の控除が認められないといこうとです。
つまり、多額の支出をしたことにより仕入時に支払った消費税のほうが、受け取った消費税よりも大きい場合でも、消費税の還付されることはありません。
また、取引先が課税事業者の場合、免税事業者との取引では仕入税額控除ができないため、取引先にとって不利になることがあります。
つまり、不利になる取引自体が見直され、免税事業者との取引自体が避けられる可能性があります。
4 免税事業者とインボイス制度
2023年10月から導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、免税事業者の意味合いが大きく変わりました。
インボイス制度では、適格請求書(インボイス)がないと仕入税額控除を受けられなくなります。
そして、免税事業者はインボイスを発行できないため、取引先が課税事業者の場合、取引先が仕入税額控除を受けられなくなります。
免税事業者の選択としては2通りあります。
まず、課税事業者になるという選択です。
取引先との関係を維持するために、課税事業者を選択するということです。
もう一つが、免税事業者を継続するという選択です。
これまでと変わらず、消費税の納税義務が免除されるという恩恵が受けされますが、取引先から取引自体を避けられる可能性もあります。
5 免税事業者から課税事業者への変更
免税事業者でも、希望すれば課税事業者を選択することが可能です。免税事業者が課税事業者選択届出書を税務署に提出することで行いま
す。
課税事業者になれば、インボイスを発行して取引先も仕入税額控除を行うことができますので、その事業者との取引を避ける理由がなくなります。
また、大きな金額の仕入がある場合には、仕入税額控除を利用して消費税の還付を受けることができます。
ただし、一度課税事業者を選択すると、原則として2年間は免税事業者に戻ることができないということに注意が必要です。
6 免税事業者の選択
消費税の免税事業者制度は、小規模事業者の負担を軽減するための重要な仕組みです。
ただし、インボイス制度の導入により、免税事業者であり続けることのメリットとデメリットを慎重に検討する必要がでてきました。
状況に応じて、課税事業者への変更を検討することも重要です。
税理士などの専門家に相談し、事業規模や取引先との関係を考慮して最適な選択をすることが求められます。
株式投資で確定申告が必要な場合と不要な場合 個人事業主から法人化するタイミングはいつがよいのか